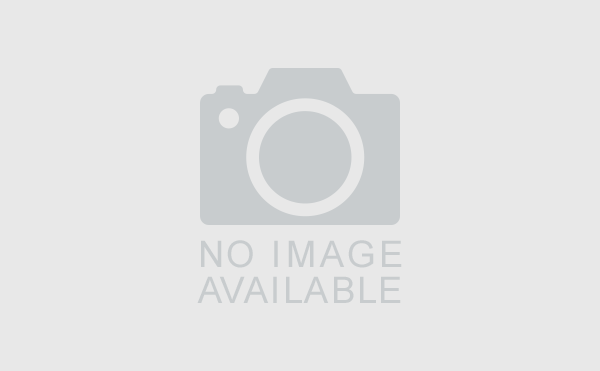「ハラスメント防止宣言」について、専門家として思うこと。
パワハラ相談(全国対応)
電話・メール無料窓口は以下から!
私たち職場環境改善工房は、以下のお電話でハラスメント相談を承っております。
基本は、10:00~18:00です。※但し、すぐに出られない時がありますので、その時は折り返します。
電話での相談はこちらから
また、メールフォームのご相談も、以下のボタンをクリックしてできます。
ちなみに、相談員のプロフィールは、こちらになります。
目次
企業における「ハラスメント防止宣言」に思うこと。
最近では、ハラスメント防止法がパワハラ・セクハラ・マタハラにまで広がった故に、企業において、「ハラスメント防止宣言」を出して、明らかにしているところも増えてきました。
職場の「安心」と「信頼」を守るために、企業が自ら「ハラスメント防止宣言」を掲げることは、一見すると当然の流れのように見えます。
しかし、現場を見続けてきた立場から言えば、「宣言」があるだけでは、実際の防止や再発抑止にはつながらないことが多いのです。むしろ、宣言を出したことで「やるべきことはやった」と満足し、実際の体制整備や教育が止まってしまうケースすらあります。
宣言は「ゴール」ではなく、「スタートライン」にすぎません。
宣言の意義 ― 組織の姿勢を見せる第一歩
まず、宣言を出すこと自体には大きな意義があります。
「この会社ではハラスメントを許さない」という意思を明文化し、社員・取引先・社会に向けて発信することは、組織の価値観を明確に示す行為です。特に中小企業などでは、制度が未整備な分、経営者がその姿勢を言葉にすること自体が、抑止力や信頼形成につながります。
また、宣言を出すことで、企業は自らに「説明責任」を課すことになります。
ハラスメントが発生したとき、「方針がなかった」「担当がいなかった」と言い逃れする余地はなくなります。これは、法令遵守(コンプライアンス)の観点からも重要です。
宣言の落とし穴 ― 「形だけ」で終わらせないために
一方で、宣言を出すことが目的化してしまうと、非常に危険です。
経営者や人事担当者が「書面を作ったからもう大丈夫」と思ってしまえば、それは形骸化の第一歩です。実際、現場では次のような課題がよく見られます。
- 相談窓口が名ばかりで、担当者が教育を受けていない
- 管理職が「自分はパワハラの加害者かもしれない」と考えたことがない
- 相談があっても、調査も是正も行われない
- 宣言文が社内で誰にも読まれていない
このような状態では、「宣言」はむしろ不信の象徴になってしまいます。
実効性を高めるための3つの要素
専門家として私が最も強調したいのは、「制度」「意識」「透明性」という三つの軸です。
1. 制度 ― 運用できる仕組みをつくる
相談窓口・調査手順・再発防止策を明確に定め、担当部署や責任者を明示すること。
外部の専門家(社労士・弁護士など)と連携し、第三者性を担保することも重要です。
また、相談者のプライバシーを守りつつ、被害を放置しない明確なルールを整えることが不可欠です。
2. 意識 ― 管理職教育と現場の自覚
ハラスメントの多くは、無自覚な言動から始まります。
「叱責」と「威圧」、「指導」と「支配」は紙一重。
だからこそ、管理職自身が「自分も加害者になり得る」という意識を持つことが重要です。
企業は年1回の研修だけでなく、日常的な振り返りの場を設けるべきです。
3. 透明性 ― 結果と改善を公表する
宣言を掲げる以上、その実行状況を外部にも説明する責任があります。
通報件数や再発防止策の実施状況などを、個人が特定されない形で開示することは、企業の信頼を高める第一歩です。
「隠す」よりも「見せる」姿勢が、社員にとって最大の安心となります。
「宣言を動かす」ための小さな実践
宣言を「動くもの」にするためには、完璧を目指さず、「できることから始める」姿勢が大切です。
たとえば、
- 毎月1回、職場ごとの「感じた違和感」共有会を開く
- 匿名アンケートで職場風土を測る
- トップが定期的に「職場の安心」についてコメントを発信する
こうした小さな実践の積み重ねが、組織文化を変えていきます。
専門家としての結論 ― 宣言とは「関係の約束」である
「ハラスメント防止宣言」とは、単なる社内通知やPRではなく、**組織と社員との「約束」**です。
それは、上下関係を超えた信頼の契約であり、互いに人として尊重し合う文化をつくる宣言でもあります。
法律や制度は、その約束を支える道具にすぎません。
真の意味での「防止」は、組織の一人ひとりが、自らの言葉と行動で「安心して働ける場を守る」意志を持ったときに初めて実現します。
だからこそ、宣言を出すこと自体がゴールではなく、
そこからどれだけ誠実に行動を積み重ねられるか――
その実践こそが、企業の本当の品格を問われるところだと、私は考えます。
私たちは、ハラスメントのご相談 承っております。
私たちは、パワハラ、セクハラ等のお悩み相談も承っております。
是非、ご相談ください。
以下のフォームからご相談ください。




.jpg)