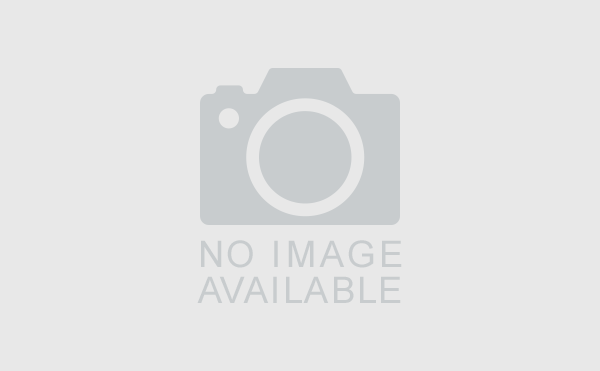パワハラにならない言葉。その境目とは? ~指導とハラスメントの狭間で考える言葉の力~
パワハラ相談(全国対応)
電話・メール無料窓口は以下から!
私たち職場環境改善工房は、以下のお電話でハラスメント相談を承っております。
基本は、10:00~18:00です。※但し、すぐに出られない時がありますので、その時は折り返します。
電話での相談はこちらから
また、メールフォームのご相談も、以下のボタンをクリックしてできます。
ちなみに、相談員のプロフィールは、こちらになります。
目次
はじめに:言葉に潜む“線引き”の難しさ
職場で使われる言葉――たとえば上司から部下への指摘、注意、依頼――その中には一歩踏み外せば「パワハラ」に変わってしまうものがあります。
相談窓口には、「これはパワハラか?」と悩んで連絡をくださるケースが少なくありません。
実際、このコラムでも、被害相談の中で「びっくりするような言葉」が報告されており、裁判でハラスメントとして認定された言葉例も紹介されています。
このような事例を通じて学べるのは、「言葉そのもの」よりも「関係性・文脈・繰り返し・受け手の感じ方」が、ハラスメントかどうかを左右する要素であるということです。
本稿では、まず相談事例・裁判例を参照しながら、パワハラにならない言葉とは何か、そしてその境目を見極めるための視座と実践的指針を提示します。
1. 事例と裁判例で見る「言葉の強さ」
1.1 裁判で認定された言葉
この記事では、「裁判で認められた言葉一覧」が紹介されています。 パワハラやセクハラの相談を無料で行っています。
裁判所が「パワハラと認めた言葉」は、一見すると過激すぎるものだけでなく、言い方や反復性、被害者の置かれた状況を重視して判断されたものも含まれています。
こうした言葉は、単発で「厳しい指摘」に見えたとしても、被告側の権力性や継続性、被害者の心理的影響まで含めて評価されたものです。
1.2 相談で見られる「びっくり言葉」
記事には、相談を受けた実例として、録音された発言、メールで送られた言葉、極端な人格否定・脅迫的表現などが挙げられています。 パワハラやセクハラの相談を無料で行っています。
例えば:
- 「犯罪者扱いする」「覚悟しておけ」「懲戒解雇だ」などの脅迫的表現
- 「化粧がなっていない」「口が臭い」など、業務と関係ない外見・人格攻撃
- 「退職してから言え」「家族に話す」など、業務外の人格・生活圏への干渉
- 「社会人として当然だろ」「言い訳をするな」など相手を一方的に責める文脈
こうした言葉は、受ける側に「自分が否定された」「逃げ場がない」「精神的圧迫を感じた」という印象を与えやすく、被害感情の形成につながります。
2. パワハラにならない言葉とは? 境目を見極める4つの視座
言葉そのものだけでハラスメントかどうかを判断するのは極めて困難です。以下の四つの視座を軸に置くことで、より合理的な判断が可能になります。
2.1 権力性・上位性
上司部下などの上下関係、不均衡な力関係がある場面においては、同じ言葉でも受け止められ方が大きく異なります。
たとえ穏やかな口調であっても、上位者が指示・強制力を帯びて発した言葉には、被った側が従わざるを得ないプレッシャーを感じるケースがあります。
2.2 継続性・反復性
単発の注意や指摘であれば「指導の範囲内」と判断される可能性が高いですが、同じような言葉を繰り返す、何度も指摘を重ねることによって、被害者の心理的負荷は累積します。
繰り返される文脈での言葉は、「日常化」「慣らし」のような圧迫感を生み、ハラスメントと認定されやすくなります。
2.3 意図・目的性
指導・業務改善を目的とした言葉なのか、それとも相手を貶める・屈服させる意図があるのか。
意図性は証明が難しいものの、発言直後の補足説明、感情の込め方、発言後の行動(フォローがあるか、誤解を解くかどうか)などが判断材料になります。
2.4 受け手の受け止め方・影響
最終的には、言葉を受けた人がどう感じたか、精神的にどのような影響を受けたかが重要です。
被害者が深く傷つき、業務に支障をきたしたり健康を損なったりするならば、それは指導の範疇を超えている可能性があります。
ただし、受け手が過敏すぎるという理由で一律に否定するわけではなく、合理性・客観性の視点で判断する必要があります。
3. 「パワハラにならない言葉」を使うための実践的指針
境目を理解した上で、実務上で心がけたい表現やプロセスを以下に整理します。
3.1 具体的・建設的な表現を使う
- 「進捗が遅い」→「このプロセスで何が滞っているか具体的に教えて」
- 「いい加減にしろ」→「ここを改善してほしい。こういう基準を満たして願う」
- 「仕事できないな」→「この部分でこういう能力・成果が期待されるので、改善案を一緒に考えましょう」
抽象的な否定・人格攻撃ではなく、具体的な課題を示し、改善を促す表現が望ましいです。
3.2 相互責任・協働のトーンを持つ
指導者と被指導者が向き合う関係性を意識し、「一緒に」改善していく姿勢を示すと、受け手の反発感が和らぎます。
「君だけが悪い」論調よりも、「この点をどう変えていけるか一緒に考えよう」というスタンスが大切です。
3.3 フィードバック前後の配慮とフォロー
注意・指摘をしたら、発言前後に配慮をし、受け手の反応を確認することが望ましい。
指摘後に意図が誤解されたまま放置せず、フォローアップの機会を設け、相手の意見や感想を聴くようにしましょう。
3.4 記録・証拠を残す
言葉は消えますが、記録(議事録、メール文面、メモ等)が残ると、後の判断材料になります。
注意・指摘を文書で補足しておくことで、「これは業務上の改善を目的としたものだ」という裏付けを持たせることができます。
3.5 一線を超えている可能性に備える
過度な人格否定、脅迫、感情的罵倒、業務と無関係な指摘、家庭・プライベートへの干渉、継続的攻撃などが見られたら、それは明らかにラインを超えている可能性が高いです。
こうした言葉を受けた側・第三者が「パワハラ」と感じる可能性を常に念頭に置いて、発言前に自問する態度を持つことが重要です。
4. ケース別シミュレーション:言葉の“揺れ”を読む
以下、具体的なシチュエーションを想定し、「パワハラにならない言葉」「危険域」「ハラスメントとされやすい言葉」例を比較してみます。
| 場面 | 指導(許容されやすい表現) | 危険な揺れ方 | ハラスメントになりやすい言葉 |
|---|---|---|---|
| 進捗遅延 | 「進捗が遅いようですが、どこが止まっているか教えてください」 | 「このままだとまずいよ」 | 「お前はやる気がない」「こんな仕事もできないのか」 |
| 仕事のミス | 「この部分でミスが出ています。次はこう直してほしい」 | 「またこれか…」 | 「何度言わせるんだ」「まるで使えない」 |
| 対応期限 | 「来週までに仕上げてくれますか?」 | 「いつできる?」 | 「期限守れないなら給料下げる」「使えないやつ」 |
| 部下の立ち振る舞い | 「報連相の頻度を増やしてほしい」 | 「もっとちゃんとしてほしい」 | 「だらしない」「常識ない」「顔見て話せないのか」 |
このように、言葉の選び方やトーン、前後のフォローによって「安全域」から「危険域」への揺れが起こることがわかるでしょう。
5. 組織・制度視点からの補完:言葉だけに頼らない仕組みづくり
言葉選びを慎重にする一方で、個人の努力だけでは限界があります。組織として以下の制度的な補完が必要です。
5.1 通報・相談窓口と予防制度
万一、言葉をめぐるトラブルが起きたときに中立公正に扱える通報窓口・調査体制が不可欠です。
匿名相談、相談者保護、第三者委員会の設置などが考えられます。
〈効果〉
この仕組みにより、従業員は「声を上げても守られる」という安心感を持ちやすくなります。
早期相談・早期是正が可能となり、問題の深刻化を防ぎ、離職や訴訟リスクの軽減につながります。
また、組織全体の「風通し」が良くなり、予防的ガバナンスが機能し始めます。
5.2 教育・研修・ロールプレイ
管理職・リーダークラスには定期的に研修を行い、言葉遣いや対応力を磨かせること。
具体的事例・演習を通じて、どう言えば改善につながるかを体得させるべきです。
〈効果〉
管理職の言動が安定し、指導の質が向上します。
部下の受け止め方のばらつきが減り、職場での信頼感が高まります。
さらに、指導スキルが「共通言語」として浸透することで、職場文化全体が成熟していきます。
5.3 フィードバック・モニタリング
定期アンケート、360度評価、意見収集などで「言葉の実際の受け止め」をモニタリングし、制度を見直していく仕組みを設けることが大切です。
〈効果〉
従業員のリアルな声が見える化され、現場との温度差を把握できるようになります。
これにより、「問題が起きてから動く」ではなく、「起きる前に改善する」予防型の運営が可能となります。
また、経営層にとっては職場のリスク指標を早期に掴める大きなメリットとなります。
5.4 リスク管理・ガバナンス統合
言葉の暴走が労務トラブル・訴訟リスクにつながることを認識し、ハラスメント対応をコンプライアンス・ガバナンス体系に組み込むべきです。
〈効果〉
ハラスメント対策が「一部署の業務」ではなく、「企業全体の責任」として位置づけられます。
経営・人事・法務・現場が一体となることで、対応の一貫性と透明性が高まり、社会的信頼の向上につながります。
さらに、企業ブランドの向上や採用力の強化といった、長期的な効果も期待できます。
このように、制度を整えることは「ルールを増やす」ことではなく、
人が安心して働ける“安全基盤”を築くことそのものです。
それが、言葉を守り、人を守る組織づくりの要となります。
おわりに:言葉を守ることは人を守ること
「パワハラにならない言葉」というテーマは、単なる表現論ではなく、人の尊厳を守るという根本命題につながります。
言葉は、人を励ますことも、傷つけることもできる。その振れ幅を意識することが、健全な組織文化をつくる第一歩です。
相談事例に触れながら学ぶと、私たちは「この言葉は許された指導か」「この言葉は被害になる可能性があるか」という線を、常に自分自身で問い続けなければなりません。
企業や上司・管理職はもちろん、被指導者であっても、自分に向けられた言葉をただ受け止めるだけでなく、「なぜこの言葉を言われたか」「背景にある力関係や意図は何か」を問い、必要なら助言を求める態度が肝要です。
そして、制度と文化が追いつくことで、言葉と人を守る職場が少しずつ実現されていくのだと信じています。
私たちは、ハラスメントのご相談 承っております。
私たちは、パワハラ、セクハラ等のお悩み相談も承っております。
是非、ご相談ください。
以下のフォームからご相談ください。




.jpg)