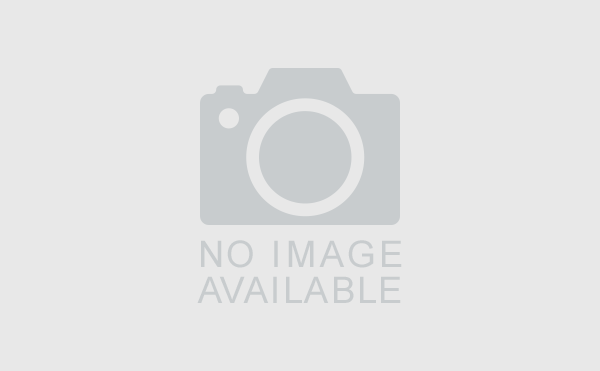セクハラ発言の本質とは? その心理的構造を見る
パワハラ相談(全国対応)
電話・メール無料窓口は以下から!
私たち職場環境改善工房は、以下のお電話でハラスメント相談を承っております。
基本は、10:00~18:00です。※但し、すぐに出られない時がありますので、その時は折り返します。
電話での相談はこちらから
また、メールフォームのご相談も、以下のボタンをクリックしてできます。
ちなみに、相談員のプロフィールは、こちらになります。
はじめに:なぜセクハラ「発言」が問題になるのか
セクシュアル・ハラスメント──通称セクハラ。
多くの人が耳にしたことのある言葉ですが、現実の場面では「冗談」「親しさの表現」「誉め言葉」として軽視されがちです。
しかし、その一言が、相手の心の領域を深く傷つけることがあります。
特に、上下関係のある職場や教育の場では、「笑って受け流すしかない空気」が被害を沈黙させ、見えない苦痛を積み重ねていきます。
セクハラ発言は、単なるマナー違反ではなく、相手の尊厳と心理的安全を脅かす“侵入行為”です。
本稿では、実際の相談事例と心理学的な構造をもとに、その本質を掘り下げます。
目次
第1章 セクハラ発言の奥に潜む「支配」と「無自覚」
セクハラ発言には、明確な身体的接触がなくても、人を支配する力があります。
たとえば次のような事例です。
「かわいいね」「今日は特別きれいだね」
「そんな服装だと男がほっとかないよ」
「冗談だから」「気にしすぎだよ」
こうした発言は、一見軽いものに見えますが、実際には相手の「境界線」に踏み込んでいます。
被害者の多くは、「笑ってごまかすしかなかった」「その場を壊したくなかった」と語ります。
つまり、発言者は“場の空気”を盾に、相手の拒絶を封じているのです。
この構造を心理学的に見ると、発言者は「支配欲」または「承認欲求」を投影しています。
他者を性的に評価することで、自分の優位性や影響力を確かめようとする心理です。
一方、加害者自身に悪意がない場合もあります。
しかし、「悪意がない」は「無害」と同義ではありません。
無自覚の言葉ほど、相手に深い傷を残すことがあります。
第2章 被害者が沈黙してしまう理由
セクハラの被害は、身体的被害よりも「言葉」で起こる場合のほうが、むしろ深刻です。
なぜなら、言葉による侵害は外から見えにくく、被害者が「自分の感じ方がおかしいのでは」と疑ってしまうからです。
心理的には、以下のような過程が起こります。
- 羞恥心と恐怖心
性的話題を含むため、相談しづらい。「自分が悪く見られるのでは」という羞恥が生じる。 - 自己疑念と自己責任感
「冗談を真に受けたのかもしれない」「気にしすぎたのかも」と自分を責める。 - 孤立と沈黙
相談した相手から否定される、あるいは職場で不利になることを恐れ、沈黙を選ぶ。 - 長期的な心理的影響
無力感・抑うつ・自己肯定感の低下など、精神的なダメージが続く。
この「沈黙の構造」こそが、セクハラを温存する最大の温床です。
加害者の多くは、「誰も何も言わなかった」として、無意識に行動を正当化していきます。
第3章 加害者心理の4層構造
実際の相談事例を分析すると、セクハラ発言をする人の心理には、いくつかの層があります。
- 自己正当化層
「悪気はなかった」「冗談だ」と自分を守る層。責任を回避する防衛機制。 - 支配・優越層
相手を見下す、または従わせたい心理。職場の権力構造に結びつく。 - 承認欲求層
相手の反応を通じて「自分は魅力的」「影響力がある」と確認したい。 - 感受性欠如層
「これぐらい普通」「そんなつもりじゃない」という無知・無感度の層。
このように、セクハラは単に「性的な問題」ではなく、「人間関係の力学」「自己防衛」「無自覚な差別意識」の交差点にある現象なのです。
第4章 組織文化が生む「許容の空気」
多くの職場では、セクハラ発言を「軽口」や「社交」として受け流す文化が存在します。
「いちいち問題にしていたら仕事にならない」「誰も気にしていない」といった言葉が、被害者の声を封じます。
しかし、これは単なる“空気”ではなく、構造的暴力です。
沈黙を強いる環境は、無言のうちに加害者を守り、被害者を排除する仕組みを持っています。
たとえば、相談しても「証拠がない」「相手に悪気はない」と片づけられる。
その繰り返しが、「どうせ何も変わらない」という諦めを生み、結果として組織全体の信頼を失わせます。
セクハラを防ぐには、制度以前に「文化」を変える必要があります。
具体的には以下の3点です。
- 管理職が率先して発言・行動の線引きを明示すること。
- 冗談や雑談の中に「違和感」を覚えたら、誰でも指摘できる風土を作ること。
- 苦情を上げた人を守る「報復禁止」のルールを徹底すること。
第5章 発言の被害を受けたらどうするか
セクハラ発言に直面した場合、次の手順が有効です。
- できる範囲で意思表示をする
「それは不快です」「やめてください」と明確に言葉にする。
その際、感情的にならず、短く事実だけを伝えるのがポイントです。 - 記録を残す
日時・場所・発言内容・相手の反応をメモに残す。
メール・チャット・音声など、後から確認できる証拠も有効です。 - 第三者に相談する
社内窓口、人事、労働組合、外部の専門相談(労基署・弁護士・支援団体)へ。
相談相手は、「話を否定しない人」を選ぶことが大切です。 - 心理的ケアを受ける
抑うつ・不眠・不安が続く場合は、カウンセラーや医療機関に相談を。
被害体験の整理には、専門家の伴走が役立ちます。
発言そのものは一瞬でも、影響は長期に及びます。
「小さな不快」を放置しないことが、自分と他者を守る第一歩です。
終章 「言葉」は関係をつくりも壊しもする
セクハラ発言の本質とは、性的な内容にあるのではなく、相手を“人”として扱わないことにあります。
それは、言葉を通じて相手を評価し、支配し、境界を越える行為です。
そして同時に、「無意識だから」「悪気がないから」という免罪符によって、社会全体がその構造を許容してきました。
しかし、言葉は本来、関係をつくるためのものです。
相手の尊厳を守りながらコミュニケーションをとることこそが、成熟した社会の基盤です。
「発言」に潜む暴力性を見抜き、誰もが安心して声を上げられる環境を築くことが、これからの組織と社会に求められています。
〈筆者あとがき〉
セクハラ発言の根底には、人間の無自覚な“優位性”の欲求が潜んでいます。
しかし、同時にそれを修正しようとする意識も、私たちの中に確かにあります。
「言葉を選ぶ」という小さな行為が、誰かの尊厳を守る大きな一歩になる。
そのことを、忘れずにいたいものです。
私たちは、ハラスメントのご相談 承っております。
私たちは、パワハラ、セクハラ等のお悩み相談も承っております。
是非、ご相談ください。
以下のフォームからご相談ください。




.jpg)