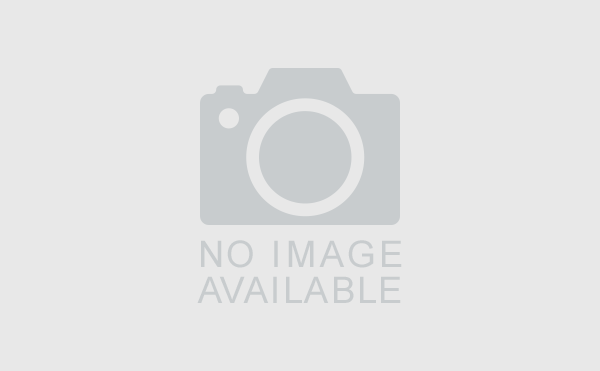『セクハラ 距離が近い』を考察する
パワハラ相談(全国対応)
電話・メール無料窓口は以下から!
私たち職場環境改善工房は、以下のお電話でハラスメント相談を承っております。
基本は、10:00~18:00です。※但し、すぐに出られない時がありますので、その時は折り返します。
電話での相談はこちらから
また、メールフォームのご相談も、以下のボタンをクリックしてできます。
ちなみに、相談員のプロフィールは、こちらになります。
私たちは、日常の仕事場・学校・各種スクール・地域活動の中で、「距離の近さ」がセクハラを招く/見えづらくさせる重要な要素だと感じています。なぜ「近い」と感じる・実際に「近い」関係が、ハラスメントを引き寄せてしまうのか。今回は、複数の相談事例・解説記事をヒントに、「近さ」と「セクハラ」の関係を深めて考えてみます。
目次
距離が近いとは何を意味するか
「距離が近い」と言っても、物理的な近さだけではありません。
- 肉体的・身体的接触が頻繁にある場面。
- 個人的な呼びかけ・馴れ馴れしさ・プライベート領域への侵入感。
- 指導・監督・教育といった関係で「ため口・友達風・タメ口+身体軽めタッチ」などが入り込む状況。
- また、「知り合い」「旧知」「上下・先輩後輩」「講師‐生徒」「コーチ‐受講者」といった関係構造が、自然と「近さ」を生んでいるケース。
例えば、あるスクールで、講師が生徒に「かわいい」「かわいい」と繰り返した上に指導時の不必要な接触があったという相談があります。
この事例では、「生徒の前でも」「数人いる中でも」「個別になった時に」身体接触+言葉かけが繰り返された、という点が「近さ」の実感を被害者に持たせたと言えます。
このように「近い」は、安心・コミュニケーションの親密さを前提としながら、被害者にとって「境界が曖昧になる」状況を含むものです。
なぜ「近さ」がセクハラを見えづらく/我慢させるか
複数の記事を参照すると、以下のような構造が浮かび上がります。
- 親密性/馴れ馴れしさが「普通/許される範囲」に紛れ込む
「講師‐生徒」「先輩‐後輩」「友人風」などの関係では、「多少のタッチ」「多少の親しげな言葉」などが“指導・交流・教育”の延長線上で「まあ良いだろう」とされがちです。 - 被害者の「これはセクハラか?」という迷い
近さによって「悪意が明白/意図的」という感じが希薄になるため、「これはセクハラ?恋愛絡み?自分が気にしすぎ?」という疑問を持たせられやすいです。 - 当事者間・周囲の目に“教育・親しみ・雑談”として“見えてしまう”
たとえば「≪生徒が何人かいる中でも講師が個別の身体接触をする≫」という行為があっても、「スクールなら指導のためのタッチだよね」「親しい雰囲気だから」などで流されることがあります。 - 相談・救済行動をためらわせる心理
「距離の近さ」が「馴れ」「暗黙の了解/友情風」「相手とのかかわり続行の希望」の中にあると、被害者は「辞めたくない」「トラブルになりたくない」「恥ずかしい」などの気持ちに縛られ、相談をためらうことがあります。 - 「近さ」が反復・継続を可能にする
物理的・心理的な遮蔽・親しみ・依存構造(スクール受講料・教室通い・先輩後輩つながりなど)があると、「断ち切りにくさ」「再接触リスク」「監視/報復の懸念」が出てきます。例として、スクールを辞めた後も「旧知の仲」ゆえに接近可能性を恐れているという相談があります。
つまり、「近さ」はセクハラを加速・隠蔽・拡散させる構造的・心理的な条件を整えてしまうのです。
ケースから見る「距離が近い」セクハラの典型
- 講師/コーチ/インストラクター → 生徒・受講者 という関係。個別レッスン・少人数制クラス・マンツーマン指導があると、身体接触・言葉かけ・距離が自然と縮まる。
- 職場で「雑談・懇親」「オフィス内での軽い身体接触」「飲み会・懇親会後のふれあい」など。「距離の近さ」が「冗談/社交」として受け止められがちだが、被害の背景では「不快・拒否できない雰囲気」が伴う。
- 男女関係・恋愛感情の錯覚/誤認も、「近さ」があるほど被害者側の判断がブレる。ある記事では「恋愛だと思っていたのに…」という相談があります。
- 被害が長期・反復・漠然としているケース。「ちょっとしたタッチ/ちょっとした言葉かけ」が、反復されることで「慣れ」が出てしまうと、距離の近さ=行為の許容化という悪循環が生まれます。
これらから、「距離を適切に保つ/境界をハッキリさせる」という観点が、セクハラ防止・救済への鍵であることが見えてきます。
対策・救済の視点:どう“近さ”を管理するか
- 自覚と整理
まず「この距離って、自分にとって『適切・安心』か?」という自己チェックが重要です。被害感・違和感を感じた時点で、記録(日時・場所・相手・行為内容)をしておくことが有効です。 - 相談・窓口活用
近い関係だからこそ、「悩んでいる=自分だけでなんとかしなきゃ」という心理になりがちですが、実際には相談を活用することが解決を早めます。 - 境界設定・物理的距離確保
たとえば「個別になるときは他者を入れてもらう」「手を出されたくない/近づられたくないという意思表示をする」「安心できる第三者に同席してもらう」といった「距離確保策」が有効です。スクール事例でも「もう通いたくない」「私に近寄らないという一筆を書かせたい」という被害者の意向があります。 - 組織的対策
指導・教育・監督をする側(スクール・会社・団体など)は、「近さ=親密さ=自由な接触」にならない仕組みを作る必要があります。たとえば、マンツーマンで“いつでも個別連絡・身体接触可能”という状況を見直す。相談窓口を明確化・匿名化・被害を訴えやすい経路を整備する。 - 再接触リスクへの備え
“旧知/知り合い/スクール継続中”という関係であれば、被害後にも“距離を詰められる・声を掛けられる・誘われる”可能性があります。辞める・関係を断つ/書面で誓約を交わすなど、被害後の「追いかけられる感覚」「距離を縮められる恐怖感」に備えることも重要です。
本質的考察:なぜ「近さ」がいけないのか
「近さ」がセクハラを助長してしまう構造には、次のような本質があると考えます。
- 力の非対称性:距離が近いということは、関係の中に「依存」「信頼」「継続」が含まれやすく、「拒否できない雰囲気」ができあがりやすい。
- 曖昧な承認・指導の境界:近さの中で「これは単なる指導」「これは友人的なコミュニケーション」「これは冗談」などが混ざると、「嫌だ/やめてほしい」が言いにくくなります。
- 心理的閉塞と孤立:近さゆえに「自分だけが変だのではないか」「周囲に言えるか」「もし言ったら目立つか/報復されるか」などを被害者が思ってしまい、声を上げにくくなる。
- 日常化と無意識化:近さの中の“ちょっとした接触”“ちょっとした言葉”が反復されるうち、「慣れ」「仕方がない」「それくらいなら…」という心理になってしまい、問題が深刻化する。
以上を踏まると、“安全で尊厳が守られる「近さ」”と“危険な「近さ」”との境界を見極めること、「適切な距離を取る文化・仕組みをつくる」ことが、組織・個人ひいては社会全体にとって不可欠であると言えます。
まとめ:距離を再考するセクハラ対策
「距離が近い」からこそ起きうるセクハラという視点をきちんと持つこと。被害者・加害者・組織すべてにとって、次のような行動がカギとなります:
- 違和感の段階で「記録・相談」をためらわない。
- “身体的・心理的・構造的な距離”を意識する/定期的に見直す。
- 組織が「近さ=信頼」だけでは済まない仕組みを作る(監督・指導・窓口・匿名性・報復防止など)。
- 被害後の「追いかけられる・再接触される」リスクにも備える。
- 相談を受ける側・聞く側が、「近さ」の中にある「危うさ」を見落とさないよう、丁寧に話を聴く・応じる体制を整える。
私たちは、ハラスメントのご相談 承っております。
私たちは、パワハラ、セクハラ等のお悩み相談も承っております。
是非、ご相談ください。
以下のフォームからご相談ください。




.jpg)