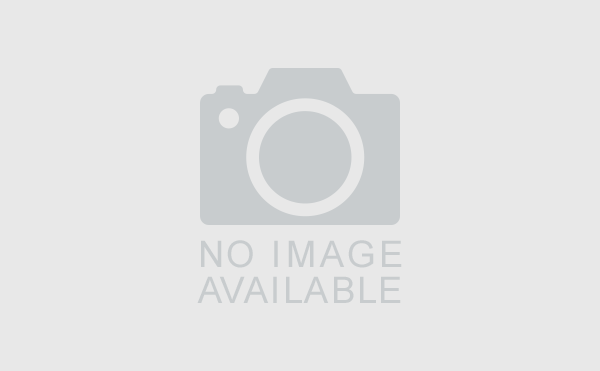ハラスメントの社会問題の本質。~何が根本解決を阻むのか~
パワハラ相談(全国対応)
電話・メール無料窓口は以下から!
私たち職場環境改善工房は、以下のお電話でハラスメント相談を承っております。
基本は、10:00~18:00です。※但し、すぐに出られない時がありますので、その時は折り返します。
電話での相談はこちらから
また、メールフォームのご相談も、以下のボタンをクリックしてできます。
ちなみに、相談員のプロフィールは、こちらになります。
目次
はじめに:なぜハラスメントは無くならないのか
ハラスメント問題が繰り返し報じられている背景には、単なる「悪い行為をする人がいる」というだけでは説明しきれない構造的・心理的な要因があります。表面的には加害者と被害者の対立構造に見えるものが、実は無数の無自覚な心理、組織文化、制度設計、社会通念、さらには相談体制の不備などが絡み合った複合問題として存在しています。
私たちが本気で「根本解決」を目指すなら、被害者救済だけでなく、加害の発生メカニズムを解きほぐし、制度・文化・意識の変革を一体で進めなければなりません。しかし、そこにはさまざまな「障壁」が働いており、これが根本解決を阻んでいます。以下、私なりに整理してみます。
ハラスメントの根底にある「防衛本能・恐れ」
pawaharasoudan.jp のコラム「ハラスメントの根本原因は、何でしょうか?」は、ハラスメント行為の心理構造を「人間の防衛本能」から説明しています。パワハラやセクハラの相談を無料で行っています。
すなわち、人は不安や恐れを感じたとき、自分を守ろうとする防衛反応を起こします。その結果として、自己正当化、責任転嫁、他者否定、攻撃的言動などを無意識に選んでしまうことがあります。たとえば、「自分の正しさを証明したい」「自分を否定されたくない」という恐れから、相手を屈服させようとする言動をとってしまう。こうした心理が、ハラスメントの根底にあるという分析です。
この視点は極めて重要です。というのも、加害者・被害者双方には「不安・恐れ」が関わっている可能性があり、それを無視したまま「規則を作ればいい」「罰すればいい」という発想だけでは、いつまで経っても表面的な抑止にとどまるからです。
抑止策と現実のズレ:制度・研修・相談体制の限界
制度・ルールだけでは不十分
日本では近年、職場におけるパワハラ防止法制などが強化され、企業にはハラスメント防止策を講じる義務が課されています。組織開発・人材育成|ALL DIFFERENT(旧:ラーニングエージェンシー)+1 しかし、ルールや制度を整備しただけで、現実の職場風土が変わるわけではありません。制度を運用する側(人事・管理職)がその意義を理解せず、形骸化させてしまうケースも目立ちます。
また、相談窓口が設置されていても、被害者が「報復されるのではないか」「相談しても無意味だ」という恐怖を抱えて利用できないという現実は、制度だけでは解決できない心理的障壁を示しています。
研修・講習が“形だけ”になる
ハラスメント対策として研修を導入する企業は多くありますが、研修だけでは問題の核心まで到達できないことも多いです。実際、研修を受けた後、半年や1年を経るうちに無意識に元の言動に戻ってしまう例が報告されています。人事部+1 また、「ハラスメント研修=加害者扱いされるかもしれない」という抵抗感から、参加者が心を閉ざしてしまうケースもあります。人事部
研修がうまく機能するためには、「知識を伝える」だけでなく、「体験的気づき」「無意識バイアスへの洞察」「感情面へのアプローチ」などを伴う内容でなければならない。その意味で、研修設計の質や参加者の意識変換をどう促すかが極めて重要になります。
相談体制・セカンドハラスメントの問題
相談窓口があっても、それを機能させるには「信頼性」「守秘義務」「公平性」「後続フォロー」などが不可欠です。相談者が、二次被害(セカンドハラスメント)を恐れて声をあげられないことが大きな障害になります。iec.co.jp たとえば、「相談したら風評になった」「被害を否定された」「逆に責められた」という経験が被害者を追い詰め、結果的に沈黙を強いることになります。
また、相談窓口そのものが内部処理中心で、「被害者に寄り添う支援」よりも「組織防御」が先行してしまう例もあります。
なぜ根本解決は難しいのか:多層的な障壁
ここまでで述べたように、「心理的要因(防衛・不安)」「制度運用のズレ」「研修と意識変化のギャップ」「相談体制・二次被害リスク」などが複雑に絡まり合っています。これらが、根本解決を阻む障壁です。
さらに加えて、以下のような要因もあります:
- 文化・通念・価値観
日本社会には、上下関係・年功序列・和・空気を読む文化などが強く根づいています。こうした文化風土の中では、「上司の指導」「役職者の言動」は暗黙に許容されやすく、受け手も抑圧を抱えることがあります。 - 責任の曖昧さ・利害調整
組織としてハラスメント問題を表に出すと、イメージダウンやリスクを避けたいという思惑が働きやすく、問題を隠蔽しようとする動きが出ることがあります。 - 意識の非対称性
加害者側には、自分の言動を「普通」「指導」「当たり前」と認識している感覚があり、被害者の視点・被害感情に気づきにくい。そのギャップに介在するのは無意識的なバイアスや感情防衛です。 - 持続性・フォローの不足
一時的な施策(研修、ポスター、宣言など)を導入しても、持続的なフォローアップがなければ風化します。本質的な意識変化や文化変革は、長期的な取り組みを要します。
本質的な解決へ向けて:私の考える論点
では、「根本解決」を目指すには、どのような方向性が必要か、私なりの枠組みを以下に示します。
1)「恐れ・不安」と向き合う組織・個人の心理変容
加害側・被害側双方にある「恐れ・不安」に向き合う場が不可欠です。自己防衛的反応を無意識に起こしてしまう自らを知り、感情を扱う力を育てることが、言動変容の土台になります。
そのためには、心理ワーク、自己省察ワーク、対話型ワークショップ、メンタリング、信頼関係構築の訓練などが組み込まれるべきです。
2)制度と文化を統合的に設計する
制度(ルール・相談窓口・処罰)と文化(信頼・対話・尊重)の両方を育てる統合的な設計が不可欠です。制度だけ先行しても、文化が変わらなければ意味が薄くなります。逆に文化だけでは、線引きや対応の公平性・持続性が担保できません。
この設計には、組織内外の第三者視点(外部相談機関、アドバイザー、コンサルタント)を導入することも有効でしょう。
3)研修・教育の「気づき化」への強化
知識伝達型の研修だけでは弱く、参加者が自ら気づき、自ら変えようと思える体験型プログラムが重要です。無意識バイアスに気づかせたり、価値観のズレを可視化したり、実際の事例を通じて感覚的理解を促す仕組みが必要です。
また、「継続型学習」を設け、研修後の振り返り、支援体制、フォローアップを制度的に組み込むことが不可欠です。
4)信頼性ある相談・支援機能の強化
相談者が安心して声をあげられる体制、かつその後のプロセスをフォローできる支援ネットワークが必要です。相談過程でのプライバシー保護、被害者ケア、中立調査、是正措置実行、被害者の再出発支援など、包括的支援が求められます。
また、相談窓口が「形だけ」にならず実効するよう、運用体制・評価制度を明確にすることも肝要です。
結びに:できること、始めること
ハラスメント問題の本質とは、単なる言動の問題ではなく、その言動を生み出す心理・文化・制度・構造の重なり合いです。根本解決を妨げているのは、私たち自身の恐れ、不安、無自覚なバイアス、変革への抵抗、制度と文化の不整合などです。
ただ、それらは「不変なもの」ではなく、変えうるものです。個人が自らの心と向き合い律し、組織が制度と文化を丁寧に設計し、相談支援を実力あるものに育てる――そうした地道な取り組みの積み重ねこそが、ハラスメントの根本解決につながると私は信じます。
まとめ:「ハラスメントの社会問題の本質」
―何が根本解決を阻むのか―
ハラスメントの根本には、「恐れ」と「不安」に基づく人間の防衛本能がある。人は自分を否定されたくない、支配を失いたくないという心理から、無意識に他者を攻撃したり抑圧したりする。これが加害の温床となる。
制度上は防止法制や研修が整ってきたが、現実の職場では「形だけ」で終わることが多い。研修は知識伝達にとどまり、相談窓口は報復への恐れで機能せず、組織はイメージ防衛を優先して問題を隠す。ここに、制度と文化の断絶がある。
また、日本社会の上下関係や「空気を読む」文化が、被害者の沈黙と加害者の無自覚を助長している。こうした文化的背景が、法制度による是正を難しくしている。
根本的な解決には、①恐れや防衛心理への理解、②制度と文化の統合設計、③体験型・継続型の教育、④信頼できる相談体制の確立、が必要である。つまり、「人を変える」ことではなく、「人の心と仕組みの両方を変える」ことが本質である。
ハラスメントは、誰か一人の悪意ではなく、社会全体の未熟さが映し出された鏡である。恐れに気づき、他者を尊重する文化を再構築することこそ、真の意味での「根本解決」への第一歩だと私は考える。
私たちは、ハラスメントのご相談 承っております。
私たちは、パワハラ、セクハラ等のお悩み相談も承っております。
是非、ご相談ください。
以下のフォームからご相談ください。




.jpg)